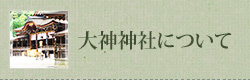



冬至の日に南瓜を食べると「病気にならない」と古くから各地で言い伝えられています。昔は冬至の頃には食べられる野菜が少なかった為、冬を元気に越せるようにと願いを込めて、栄養もあり保存の利く南瓜を大切にし、食べられていたようです。
そこで当神社では、冬至の時期にあわせて奉納され、御神前にお供えされた南瓜を大鍋で炊き出して、参拝者の方々に振る舞っております。
例年1200食分を用意し、周囲は南瓜と出汁の香りが立ちこめ、事前の告知でご存じだった方や、偶然この日に参拝した方々などで会場には人があふれ、大変喜ばれています。
当日は祈祷殿前にて「南瓜煮」と「南瓜ぜんざい」を各600食(※無くなり次第、終了)ずつご参拝の皆様に無料で振る舞います。是非お楽しみに。
来る平成30年は戊戌(つちのえいぬ)歳にあたります。 干支の「縁起物」を家に飾ると一年中、災難無く過ごせると言われています。 「来年の縁起物を飾って、新年を迎えたい」と願う人たちも多く、12月1日より社頭では干支のお守や一刀彫、色紙などの縁起物の授与を開始。 来るべき戌歳にはご家族おそろいで、神気満ちわたる三輪大神様のご神前にお詣りいただき、新しい年の無病息災と開運招福をお祈り下さい。
【12月1日より開始の授与品】
・干支絵馬 ・干支色紙 ・干支守陶器(大・小) ・干支守一刀彫(大・小)
・招福えと守 ・昇運えと守
・玉かげ寶來 ・三輪寶來
【12月15日より開始の授与品】 ※矢・扇の郵送は出来ません。
・福矢(大 2500円 小 1500円) ・厄除破魔矢 ・福扇(大・中・小)
―ご出品いただく学校・塾先生方へのお知らせー
今年も奈良県を中心に小・中学校・高等学校・特別支援学校や書道塾の児童・生徒さんを対象に書初めまつりを開催いたします。 開催にあたり、例年ご出品いただいている学校・塾先生方のご要望により課題、要項を御案内することとなりました。出品には、団体整理番号の入った出品票・出品目録が必要となります。
【個人での出品は受け付けておりません】
要項をよくお読みいただき、間違いのないようご出品下さい。明治祭並講社崇敬会神符頒布祭
11月3日(金・祝) 午前 10時
文化の日、明治祭に併せ講員・崇敬会員の安全をお祈りし、新しい御神符が頒布されます。
献詠祭並第14回三輪山まほろば短歌賞表彰式
11月3日(金・祝) 午後 1時
記紀万葉の昔から数多くの秀歌に彩られてきた三輪山に対する人々の憧憬の念は、今も変わりません。
この日、献詠祭が斎行され、祭典では「第14回三輪山まほろば短歌賞」で応募された作品の内、前川佐重郎先生・奈賀美和子先生・藤岡きぬよ先生による厳正な選により「入選」となった秀歌が披講されます。今回は相聞歌(愛の歌・人に贈る歌)、自由歌或いは題詠「海」を歌題とする短歌を募集しました。
「献詠祭」に引き続いて「表彰式」が執り行われ、入賞者には賞状・賞品が授与されます。
醸造安全祈願祭(酒まつり)
11月14日(火) 午前 10時30分
例年11月14日に、「酒の神様」「醸造の祖神」と仰がれるご神徳を称えて、新酒の「醸造安全祈願祭(酒まつり)」が行われます。
お祭りにあわせて、南西廻廊においては7~14日まで「全国銘酒展」、そして11・12・14日には、拝殿前の特設テントにおいて醸造元より奉納された四斗樽の鏡が開かれて参拝者に振る舞われ、境内一円がお酒の甘美な香りで満ち溢れます。
新嘗祭(しんじょうさい・にいなめさい)
11月23日(木・祝) 午前 10時
「新嘗祭」とは、春の五穀豊穣を祈る「祈年祭」に対し、秋の稔りに感謝するお祭りです。
宮司の祝詞奏上に続き、四人の巫女により神楽「磯城の舞(しきのまい)」が特別に奉奏されます。
古来より重要とされるお祭りのひとつで、大祭式で行われます。
また、「第46回農林産物品評会」が開催され、午後1時からは即売も行われます。
11月18日と19日の両日は「関西文化の日」です。
関西文化の日とは、関西元気文化圏推進協議会と関西広域機構の共催にて毎年11月に開かれている文化イベントで、近畿2府4県に三重県、福井県、徳島県、鳥取県を含む地域で美術館、博物館、資料館等の文化施設(原則として常設展示)を入館無料で開放し、美術・芸術に親しんでもらい、関西地方の魅力ある文化作りを楽しんでもらうため実施しています。
当神社にも境内祭祀遺跡出土品、重要文化財の「楯」、県指定文化財の「御神像」をはじめ、鏡、古絵図など多数のものが納められ、展示される「宝物収蔵庫」が祈祷殿前にあり、11月18日と19日の両日は無料公開いたします。是非この機会にお立ち寄り下さい。
男の子は三歳と五歳、女の子は三歳と七歳と、成長の節目にあたる子供たちが神社にお参りして、これまでの健やかな生育と健康を感謝し、なお一層の成長を願うのが「七五三詣」です。
当神社では、10月・11月の二ヵ月間にわたり、毎日「七五三詣」のご祈祷をご奉仕致しておりますので、ご都合に合わせてお越し下さい。
お参りのお子さんには、「お守り」をはじめ「千歳飴」や「風船」などの記念品が授与されます。
どうぞご家族お揃いでご参拝頂き、大神様のご神前でご祈祷をお受け下さい。
◆受付時間 9時から16時までの毎日(ご予約は不要です)
◆ご祈祷料 5,000円(お二人の場合、お二人で8,000円)
※神楽祈祷の場合、10,000円(お二人の場合、お二人で18,000円)
奈良市の中心地にある率川神社(いさがわじんじゃ)は、奈良市内で最古の神社です。社殿が三殿、横に並び、左右に父神様(狭井大神)と母神様(玉櫛姫命)が、まるで中央の御子神様(媛蹈韛五十鈴姫命【ひめたたらいすずひめのみこと】)を、お守りするようにお祀りされています。
このことから「子守明神(こもりみょうじん)」とも呼ばれ、古くより篤い信仰を集めてきました。
昨今、児童・幼児虐待など親と子の関係、きずなが弱くなり、その将来が心配される時代にあって、誠に麗しい姿で鎮座なされ、「子育ての神様」として、ご神徳を仰いで参拝される方も年々多くなっています。
10月、11月中は毎日「七五三生育安全」のご祈祷を受付けていますので、是非ご参拝下さい。
その他のご祈祷も毎日承っております。
◆受付時間 : 10時から15時まで(事前にお電話にてご予約下さい)
◆ご祈祷料 : 5000円から
◆お問い合わせ : 奈良市本子守町18 率川神社 (電話)0742-22-0832
