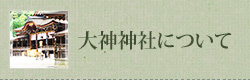

「節分祭」・「福寿豆撒式」
2月3日(土) 午前11時
節分祭は年男・年女の方々が多数参列して厳かに執り行われ、4人の巫女により神楽「奇魂の舞(くしみたまのまい)」が奉奏されます。祭典終了後、引き続き拝殿より「福寿豆撒式」が、裃(かみしも)すがたの年男・年女や崇敬者により賑やかに奉仕されます。 また撒かれる福餅の中には大国様のお面など景品の当たる「特賞」、「一等賞」、「二等賞」などの福引番号が書かれた紙が入っており、社頭は福をいただこうとする参拝者で賑わいます。
立春祭
2月4日(日) 午前 10時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
一年の始まりであり、暦の上で春を告げる立春の日に行われるお祭りです。
卜定祭(ぼくじょうさい)
2月5日(月) 午後2時
5日の午後2時より、地元特産「三輪素麺」の新しい年の販売価格を占う「卜定祭」が執り行われます。祝詞奏上の後、古式に則って卜定が行われ、ご神意のまにまに素麺の卸値として「高値」「中値」「安値」の中から今年の価格が決まります。 また祭典後、拝殿前斎庭で三輪素麺掛唄保存会の皆さんによる踊り「三輪素麺掛け唄」も奉納されます。
おんだ祭・豊年講大祭
2月6日(火) 午前10時30分
このお祭りは、年の初めにお米をはじめとして穀物の豊穣を祈るお祭りです。 拝殿向拝を「神田」に見立て、烏帽子に白丁姿の田作男(たつくりおとこ)が軽妙な語り口でおもしろおかしく農耕の所作を行います。そして、2人の早乙女がお田植えの所作や鈴神楽を舞い、神前に供えられた「籾種」が田作男によって参拝者にまかれます。 特にお田植え神事は数ある当神社のお祭りの中でも、異彩を放ち、古式を感じさせるものとなっています。
紀元祭
2月11日(日・祝) 午前 9時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
神武天皇が即位された「紀元節」の日であり、現在は「建国記念の日」として、これを祝う「紀元祭」が行われます。
第65回書初めまつり奉納奉告祭・表彰式
2月11日(日・祝) 午後1時
学業に励む児童生徒の、真心こもる書初め作品を奉納していただき、なお一層書道の盛んになることを祈る、「書初めまつり」(主催 大神神社・奈良県書道教育研究会、後援 奈良県教育委員会・読売新聞奈良支局)が執り行われます。 祭典終了後、大礼記念館2階大広間において「表彰式」を行い、「大神神社宮司賞」と「奈良県書道教育研究会賞」の各受賞者の中で当日ご出席の方を表彰します。(奉告祭・表彰式にはどなたでも参加可能です) 厳正なる審査により選ばれた「大神神社宮司賞」「奈良県書道教育研究会賞」「特選」「準特選」「優秀」の各賞の入賞作品の展示は、大礼記念館2階大広間にて2月11日から13日(午前9時から午後4時)まで行われます。
祈年祭
2月17日(土) 午前10時
繞道祭(にょうどうさい)並皇室御安泰祈願祭
1月1日(月・祝) 午前 1時
率川阿波神社初戎
1月5日(金) 午前 10時30分参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
大とんど(古神符焼上祭)
1月15日(月) 午前 8時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
久延彦神社入試合格安全祈願祭
12月3日(日) 午前11時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
天長祭
12月23日(土・祝) 午前10時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
12月23日の天長祭では、天皇陛下のご誕生日を奉祝申し上げ、陛下のご長寿と日本の国と国民の安泰が祈られます。
天皇陛下のお誕生日と1月1日の四方拝、2月11日の紀元節はかつて三大祝日で、これらを総称して三大節と呼ばれていました。どうぞご参列ください。
大祓
12月31日(日) 午後2時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
明治祭並講社崇敬会神符頒布祭
11月3日(金・祝) 午前 10時
文化の日、明治祭に併せ講員・崇敬会員の安全をお祈りし、新しい御神符が頒布されます。
献詠祭並第14回三輪山まほろば短歌賞表彰式
11月3日(金・祝) 午後 1時
記紀万葉の昔から数多くの秀歌に彩られてきた三輪山に対する人々の憧憬の念は、今も変わりません。
この日、献詠祭が斎行され、祭典では「第14回三輪山まほろば短歌賞」で応募された作品の内、前川佐重郎先生・奈賀美和子先生・藤岡きぬよ先生による厳正な選により「入選」となった秀歌が披講されます。今回は相聞歌(愛の歌・人に贈る歌)、自由歌或いは題詠「海」を歌題とする短歌を募集しました。
「献詠祭」に引き続いて「表彰式」が執り行われ、入賞者には賞状・賞品が授与されます。
醸造安全祈願祭(酒まつり)
11月14日(火) 午前 10時30分
例年11月14日に、「酒の神様」「醸造の祖神」と仰がれるご神徳を称えて、新酒の「醸造安全祈願祭(酒まつり)」が行われます。
お祭りにあわせて、南西廻廊においては7~14日まで「全国銘酒展」、そして11・12・14日には、拝殿前の特設テントにおいて醸造元より奉納された四斗樽の鏡が開かれて参拝者に振る舞われ、境内一円がお酒の甘美な香りで満ち溢れます。
新嘗祭(しんじょうさい・にいなめさい)
11月23日(木・祝) 午前 10時
「新嘗祭」とは、春の五穀豊穣を祈る「祈年祭」に対し、秋の稔りに感謝するお祭りです。
宮司の祝詞奏上に続き、四人の巫女により神楽「磯城の舞(しきのまい)」が特別に奉奏されます。
古来より重要とされるお祭りのひとつで、大祭式で行われます。
また、「第46回農林産物品評会」が開催され、午後1時からは即売も行われます。
久延彦神社例祭(くえひこじんじゃれいさい)
9月1日(金) 午前11時
末社、久延彦神社の御祭神は久延毘古命(くえびこのみこと)で、『古事記』には世の中のことをことごとく知っておられる知恵の神様と記され、学問・知恵の神様、学業安全や入試や各種試験の合格祈願のお社として知られています。
9月1日は久延彦神社の例祭日で、学業向上・入試合格はもとより、気力を養う身体の健康もお祈りされます。祭典終了後、神前にお供えされた「学業成就鉛筆」が参列者全員に授与されます。
郷中敬老祭
9月18日(月・祝) 午前10時
当神社の氏子区域にお住まいの数え年80歳以上のお年寄りをご招待して、「郷中敬老祭」が行われます。
敬老祭終了後、大礼記念館で記念の式典があり、宮司や自治体の関係者がご長寿の祝辞を申し上げ、記念品を贈呈します。引き続き大阪からやってきた桂米朝一門の落語家さんによる落語が催されます。
秋季皇霊祭遙拝
9月23日(土・祝) 午前10時
この日、皇居の皇霊殿において皇祖皇宗をはじめ代々の皇室の方々の御霊を祀られる秋季皇霊祭が行われるにあたり、当社でも宮司以下神職が遙か皇居を遙拝し、歴代天皇や皇室の方々の偉業を偲び奉ります。
秋の講社崇敬会大祭
9月23(土・祝)・24日(日) 午前11時
当神社を信仰する講員・崇敬会員のご安全と家運のご隆昌を祈る講社崇敬会大祭が、23日・24日の両日にわたり執り行われます。
また祈祷殿前では講社崇敬会事業実行委員会の皆様による「三輪山福袋」、「千本杵餅つき」、「各種バザー店」、「わんぱく広場」、「金魚すくい」など、楽しい催物が数多く用意されています。
七夕祭
8月7日(月) 午後2時参列自由 ※ご自由にご参列下さい。
8月7日の午後2時より拝殿にて、学業の向上・技芸の上達と諸願成就を祈願する「七夕祭」が行われます。
8月1日より拝殿前に笹竹が立てられ、参拝者のために短冊を準備、自由に願い事を書いていただけるようになっています。
綱越神社例祭(おんぱら祭)
7月30日(日) 午後4時30分 おんぱら祭宵宮祭
7月31日(月) 午前10時 おんぱら祭
午後7時30分~午後8時10分 奉納花火大会(於:桜井市芝運動公園)
「おんぱら祭」は、古式に則り執り行われるお祓い行事です。その中で「水無月(みなづき)の夏越(なごし)の祓(はらえ)する人は千歳(ちとせ)の命延ぶといふなり」の古歌を唱えながら、茅の輪を3回くぐる神事があり、このとき同時に神馬(しんめ)引きも行われます。
両日とも参拝者は境内の鳥居に取り付けられた茅の輪をくぐり、この半年間に知らぬ間についた罪・穢れを人形(ひとがた)に移し、夏の無病息災、延命長寿を祈ります。
また31日には県下最大規模を誇る「奉納花火大会」があります。